 |
 |
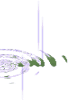 |
|
| 残雨 | |||
 |
|||
 |
 |
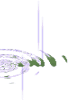 |
|
| 残雨 | |||
 |
|||
死んだ子供は いつまでも 死んだときのまま 年を取らない
わたくしのなかでは いつも あの子は はたちを出たばかりの若武者のままで
「行って参ります、母上」
颯爽と 馬にまたがって 高々と 右手を上げて
あれは 建安元年(196) 暮れのこと…
それが あの子の見納めであった・・・・・
「お方さまを…離別なさるのですか?」
なによりも、まず。信じられぬという思いが先に立つ。
「ああ。」
殿は、憮然として、杯を差し出された。杯を満たすわたしに。
「この儂がわざわざ迎えに行ったというのに、機を織り続けて…、返事もせん。儂もよくよく嫌われたものだ。…あれではないか、あいつ、儂より昴(曹昴)の方を好いておったのではないか」
「まさか、そのような」
戯言を、言いながらも。殿の目は、暗く。
「お前も、そうか?」
「え?」
「もし、儂が…、丕を戦につれて行って、死なせとしたら。丁氏のように、儂を責めるか?」
そのようなこと。その時になってみなければ…判らない。
どんな戦で、どんな死に方をしたのかにもよるし…。
このたび。子脩(曹昴)どのは。殿を庇って、亡くなったのだという。宛城陥落の折、馬を射られた殿に、ご自分の馬を差し出され…
たとえば、わが子曹丕が、そのような死に方をしたのなら。わが殿、曹操…曹孟徳どのが、丕を死なせて、そうして生きて戻ってこられたのなら。わたしは、どうするだろう。
殿を責めぬという自信など、わたしにはない。母親とは…、そういうものだろう。
けれど。歌妓であったわたしには、男の問いには、男の喜ぶ答えを返すというのが、習い性になっていたから。
「いいえ」
わたしはそのとき、そう答えた。
「おまえは…、優しいな」
ふっとお笑いになった、殿は…、わたしの嘘を、見抜いておられたのだろうか…
殿。曹操、字は孟徳。
お方さま。丁氏…、殿のご正室。
そして、わたし。歌妓あがりの側室、卞氏。
あれは、建安2(197)年の、春。
宛城のいくさで、殿は、張繍の騙まし討ちに会い、ご長男を、失われたのだった。
殿のお嘆きは、表にはお出しにならぬが…、それはそれは、おいたわしいものであった。
ご長男の御名は、曹昴…、字は、子脩。
わたしがこちらにあがる前のことで、よくは知らないが。劉氏という、早くに亡くなられた側室との間に、儲けられたお子なのだという。
劉氏さまが亡くなった後、子脩どのをお育てになったのは、お方さまで。お子のないお方さまは…、それこそ、我が子のように可愛がっておられた。
それにしても。
あのように。心を痛めておられる殿を、「わたくしの子を殺した」と、お責めになるとは。
同じ、子を持つ母として、お気持ちが判らぬではないが…、まして子脩どのは、殿のお身代わりのような形で亡くなられたのだから…、けれど。あそこまでお責めにならずともよいのにと、わたしでさえ、思った。
少し、羨ましかったのも、事実だが。
歌妓のあがりで、しっかりした実家とてない、わたしとは違い。お方さまには、丁家というしっかりしたご実家がある。
殿に捨てられたら、生きるすべを失う…、だからどうでもご機嫌を取り結ばねばならない、そんなわたしとは、違うのだ。
だから、お方さまが実家に帰されたとき、…正直に言えば、わたしの中には、「甘えているだけだ」という、冷たい気持ちがあった。殿に甘えて、ご実家まで、迎えにこさせる。お方さまは、わたしどもに比べてかなりの年嵩で…、容色とても衰えておられる。それでもこれまでは、ご長男の子脩どの義母上ということで、奥向きでは第一の地位を保っておいでになったけれど、その子脩どのが亡くなられたのだ。きっと、殿のご愛情を、そういう形で確認なさりたいのだろう。…そう、思っていた。
殿が迎えをおやりになれば、戻っておいでになる。ましてや、殿おん自らがお出かけになったのだ。戻って来られぬわけはない。
そう、思っていたのだが…
何故。
ものごとを、男と女の情からしか見ることを知らぬわたしには、お方さまのこのたびのお振る舞いは、どうにも納得のゆかぬものであった。
そして…
「卞夫人」
奥向きに仕える侍女のひとりが、わたしのもとを訪れたのは、そろそろ夏も盛りになろうかという頃であった。
「あの…、そろそろ、冬のお召し物にする布を、注文せねばならぬのですが…、どう、いたしましょう…?」
「え?」
どう、と、言われても。
そういえば、これまでは、奥向きに布が届けられ、子供の数や侍女の数に応じて、側室たちに配分されていたのだが…
「これまでどおりでは、いけないのですか?だいたい…なぜわたしに、そんなことを」
「なぜと言われましても…」
侍女は、困ったように、眉を寄せた。
「これまでは、お方さまが、そのようなことはすべて、取り仕切っておいででしたから。お方さまが…ああいうことになって、私どももどなたの指示を仰げばよいのか…、たとえば殿のお召し物ひとつにしても…」
「殿の、お召し物?」
そのようなことは、表の…、従僕なり何なりが、用意するのではないのか。そう言うと、侍女は、あきれたように首を振った。
「それは…、正式のご装束はそうですけれど、奥向きでおくつろぎになるときお召しになるものは…、お方さまが、手ずから機を織られて」
「・・・・・」
奥ではいつも、殿は…、趣味の良い、着心地のよさそうなものをお召しになっている。では、あれは…、お方さまが?
そんなことを言われても、わたしは歌妓のあがり。歌を歌い、舞を舞うことは出来ても、そのような…、機織りの心得もなければ、裁縫の腕もない。
「でも…、この夏のぶんは。ちゃんと、春先に、配られたではありませんか。何もわたしが采配を振るわずとも…」
「あれは」
侍女は、一瞬ためらって、そして、言った。
「あれは…、お方さまが、出てゆかれる前に、細かく指示をしてゆかれましたから…」
お方さまが…?
「それで、…なぜ、わたしに…?それも、お方さまのご指示?」
ひどいと、思った。歌妓あがりのわたし、良家の暮らしなど知らぬわたし。そんな…、奥向きの差配など、できるわけもないことくらい、あのお方さまはご存知であろうに。
ご自分が、離縁されたから。殿のお側に侍り続け、子まで成したわたしが、憎いから。このような仕打ちをして、愚弄なさるのか。
「いえ」
侍女はまた、首を振った。
「お方さまは、…なにも。殿が、次のご正室をお決めになるだろうから、その方のご支持を仰ぐようにと、そう仰せられて…」
「え…」
では。お方さまは、あの時すでに、…お戻りにはならぬおつもりで?
わたしは…、あれも、殿のお気を惹くためだと、考えていたのに!
自分は、何と、浅ましいことを考えていたのだろう。自分は何と心根の卑しい人間であったのだろう!
「殿からは…まだ、次のご正室がどなたとも、お伺いしておりませんし。いかがいたしましょう…」
あなたさまが、今は、ご寵愛第一のお方ですから。侍女はそう言って、わたしを窺い見る。
けれど…、そのようなこと。何をどうしてよいのやら、見当もつかず…
「わたしには、とても。お方さまに、お縋りするわけには…?」
ほっとしたように、侍女が、頷いた。
「昴を、頼みます。お頼み、申します…」
苦しい息の下で。何度も、それだけを繰り返した。縋るように、わたくしの手を握って。
わたくしと、孟徳どのの寵を争った…、劉氏。
長男を、産んで。自信を得たのであろう、とかく、わたくしをないがしろにする振る舞いが多かった、彼女。
まさか自分が、病に倒れるとは。幼子を、憎い女の手に託して死なねばならぬとは。
さぞ、悔しかっただろう。無念だったろう。
「ご安心なさい。昴どのはきっと、わたくしが、曹孟徳の跡取りとして恥ずかしくない男に育てますから…」
わたくしの言葉に安堵したように、ほっと、息を吐いて。
そうして、彼女は、逝った。
わたくしの手を、握りしめたまま。
「申し訳、ございませぬ。お方さまのお手を、煩わせまして…」
離縁された家に、呼びつけるなどと。…詫びるわたしに、お方さまは、優しく仰せになった。
静かに雨の降る、あれは…、夏の午後。
「いや、そなたの立場を思えば、已むを得ぬこと。孟徳どのがお留守で良かった」
済まなそうな顔をなさって、…お言葉は、続く。
「孟徳どののことだから、意地でも、さっさと、次の正室を迎えるであろうと思うていたのですよ。あの方の地位を固めるのにふさわしいお家から…」
…そうだった。良家にとって、婚姻というものは、そのようなもの。表の…、政や権力争いの、一環であるのだ。
殿が、そうなさらなかったのは…
「卞どのが、そこまで孟徳どののお心を捕らえていようとは。申し訳ないが…、わたくしは思うておらなんだ」
いきなり奥を仕切れといわれて、こうした家での仕来りをご存知ないそなたのこと、さぞお困りになられたであろう。済まぬことをしたと、お方さまが、わたしのようなものに頭をお下げになる。
「いいえ!いいえ、殿は…」
殿が新たな正室をお迎えにならないのは。それは…、お方さまを、思うておられるからでございましょう。そう言ったわたしに、お方さまは、苦笑を浮かべてお見せになる。
「まさか。そこまでわたくしも自惚れてはおらぬ」
「まことにございます」
ふっと、お方さまが、遠い目をなさる。ここぞとばかりに、わたしは言った。
「なぜでございます?なぜ、…あのように、殿をお責めになったのでございます?」
一番心を痛めておられたのは…、殿でございましょうに。
その時の、お方さまのお返事は。
こうして、卞皇后と呼ばれる今になっても、忘れられぬ。
「孟徳どのには、慰めてくださるお方が、幾らもおいでになろう」
「…お方さま!それは…、お辛いのは判りますが…」
「辛い…」
遠い目をしたまま。お方さまは、おっしゃった。
「わたくしの、辛さなど。もっと…、誰より辛い思いをした者が、他にいよう」
遠くを見つめておられた目が。わたしの上に、戻ってくる。
「卞どの」
幼い我が子を遺して死なねばならなんだ劉氏は、どれほど辛かったか。
愛しい我が子を、孟徳どのの寵を争った憎い女に託さねばならぬことが、どれほど悔しく、不安であったか。
その子が、願った地位にもつけぬまま、あのような死に方をして…、どれほど無念であったか。
「子を持つそなたになら、判ろうの…?」
返す言葉を、わたしは、持たなかった。
「死んでしまった側妾の味方になってやる者など、誰もおらぬ。いるとすれば…わたくしだけだと、思うた。
曹孟徳の奥を統べる、この、わたくしだけだと。」
そのまま、奥にとどまることは、どうしても出来なんだ。
それでは、あまりに…、劉氏が哀れで。
「側妾のひとりも労われぬ者に、奥を統べる資格などないであろう?」
そういって。お方さまは、微笑まれたのだ・・・・・
あの時、思い知った。
なぜ、殿が、この方を愛されたのか。
わたしなど、及びもつかぬ。
天下に女は数あれど。
殿にふさわしいのは、…お方さまだけだった。
死んだ子供は いつまでも 死んだときのまま 年を取らない
儂のなかでは いつも あの子は はたちを出たばかりの若武者のままで
「父上、私の馬を!!」
辛すぎて 振り向くことも出来なんだ儂を 追いかけるように響いた 断末魔の悲鳴
あれは 建安二年(197) 正月…
それが あの子との別れであった
そして もうじき 儂は・・・・・
「丁氏の…墓は…どこだ…?お前なら…、知って、いよう?」
「殿…」
「気づかぬと、思うてか。奥の、差配の仕方が。お前のやりかたは、あれのやりかた、そのままであった」
「・・・・・。」
「あれが…、ずっと、見てくれていたのだろう?」
「はい…」
「あれに、挨拶をして、おきたい。これから行くが、お手柔らかに、頼むと。もう、返事をしてくれぬなどというのは、ご免だ。墓も、知らぬなどと言えば…、昴にも、何を言われるか、判らんからな…」
ああ。やはり。
「ご案じなさいますな。お方さまは…、何もかも、おわかりでいらっしゃいますとも」
「…そう、だな…」
丁氏は、そういう女であったと、殿は笑って、仰せになった。
「だが…、それでは、儂の気が、済まぬ」
そう。わたしは結局…、あの方には、勝てなかった。
お方さま。
曹孟徳の、数ある、女のなかで。
卞皇后と呼ばれるわたしに、ただ一人、負けたと思わせたおかた。
女の意地と、女の誇りを。わたしに教えてくださったおかた。
「死んでしまった側妾の味方になってやる者など、誰もおらぬ。いるとすれば…わたくしだけだと、思うた。
曹孟徳の奥を統べる、この、わたくしだけだと。」
その通りです、お方さま。
殿にふさわしい女は…あなただけ。
お方さま。
丁夫人。
![]()
![]()
![]()
![]()
このページの素材は雲水亭さまでお借りいたしました